1985年2月から1988年2月までの3年間の僕の動きは、以下の順番でAからIまで9つのパートに分かれる。
当時20代後半だった男が肌で感じたことを、時系列で日記調のエッセイとして書いている。

A, B, C – オーストラリア
1985年2月から1986年11月まで
オーストラリアへはワーホリ(ワーキングホリデー)として渡航。多くのワーホリ旅行者とまったく異なり、不安や迷いの日が続いたが、徐々に海外生活と英語に慣れるに従い伸び伸びと自由かつ活発に動けるようになっていった。
パース、カラーサそしてシドニーと住む場所が変わった。そしてその1年半で自分への自信を徐々に回復するに従い、何でもやってみたいという好奇心と何でもできるという強さが備わっていった。
D, E, F – 東南アジア、ロンドン・ヒースロー空港の収容所、ヨーロッパ
1986年11月から1987年3月まで
オーストラリアのあと、さらに広い世界へと見えない何かに導かれるように、東南アジア経由のヨーロッパ行きの片道チケットを買った。
特にそれまで特に旅が好きということもなかったが、各地域を訪れ五感でその多様さをガツンと受ける刺激と心地よさを覚えていった。
東南アジアは当時まだまだ発展途上で、日常起こることがすべてエゲツないことばかりで、世界の多くはこのようなものなのかと洗礼を受けた。
そしてヒースロー空港での収容所暮らしは2泊3日と短期間だが、このストーリー全体でのハイライトの一つだ。極めて非日常的な記録をガハハと読んでほしい。
G, H, I – イスラエル、ノルウェーそして香港と台湾
1987年3月から1988年2月まで
イスラエルの2カ所は、世界中からカネなしヒマあり仕事なし好奇心ありの若者がボランティアとして集まった農場で、ミニ国連のようなところ。日本と外国との違いを改めて痛感。
ノルウェーではヨーロッパ最北端の北極圏の村で魚工場にて仕事をした。極夜(一日中太陽が見えない日)の地域で現地の人たちと外国人労働者たちとのこれまた刺激的な日々。
帰りに立ち寄った香港と台湾では2年の西洋暮らしのあとに感じた東アジアの人たちへの思いが記録されている。
何があったか、自分がどう変わったか
命の危険に遭遇したり、
極端な貧しさを目にしたり、
ほぼ無一文になったり、
収容所に入れられたり、
45℃の極暑地帯で生活したり、
マイナス20℃でヒッチハイクしたり、
紛争地帯でボランティアしたり、
一国の人気ナンバーワン歌手のコンサートの楽屋に入れてもらったり、
などなど日本では決して味わえない経験をした。
そういう稀有な経験をすることに、当時の自分はおそらく興奮みたいなものを感じていたようだ。渡航当初とは別人のように自己肯定的になって、いわばちょっとしたナルシスト状態だったと言えるのかもしれない。
まとめ
3年間に渡って書かれたこの日記エッセイは、当時の一人の20代の日本人男性の濃密なプチストーリーだ。
興味のある国の箇所だけをかいつまみ読みして、当時のその国や人のことを知るというのも自由だ。だが可能であれば最初から読むことで一人の人間が変わっていく様から何か刺激を受けてもらえるものと推測する。
長いストーリーだが、読後に何かのプラス効果を貴方に与えられていれば筆者として大きな喜びだ。
ぜひ読み始めて読破していただくことを切に願っている。


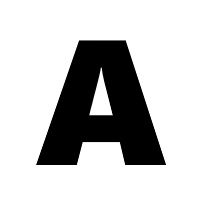



コメント