1985年5月D日
バレーボールのクラブ入会へ
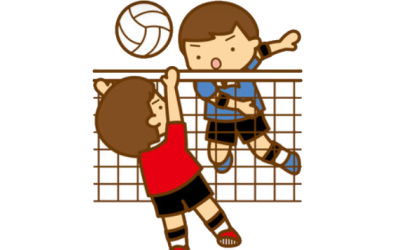
来週から当州のバレーボールのクラブに入会することができそうだ。今日、西オーストラリア州バレーボール協会の代表のところへ電話を入れてみたところ、次の日曜日にヴィクトリアパークの体育館へ来てくれ、との快い返事をもらった。
中学校、高校、大学(同好会)と、バレーボールのみを自分のやるスポーツと決めてやってきた。大学を出て4年が過ぎたが、振り返ってみれば、バレーをしていた時の自分が他の時間と比べて最も生き生きとしていたように思う。
いやバレーをしていた時だけ、自分自身が輝いていたといえるかもしれない。中学校の時に大阪府で2位になったことを除けば、ほかに人に堂々といえる成績は何ひとつ残ってはいないが、オレはあの瞬間輝いていた、と今もはっきりと言い切れるのはバレーをしていた時の自分をおいて他にはない。
職を投げうってまで、オーストラリアくんだりまでやってきたのは、英語を学びたいからでも、この国で生活したいからでも、この国の何かのスペシャリストになりたいからでも、旅行が好きだったからでもなんでもなかった。
はっきり言って、仕事に関しては自己を十分に律してきたつもりであったし、いま異国の地にて客観的に自分が日本で4年間に成し遂げた成果を見直しても、決して周りの人々にとやかく言われる筋はない、と自分を確信させるだけのことはしてきたつもりだ。
だが、私的な自分については、大学4年の時に失恋して以来、自分自身にも何故そうなったのか説明しきれない、底なしの自己嫌悪に陥ってしまった。
つまり自分がこの国へやってきたのは、私的な意味において、自分に自信が持てない自分、鏡を見たら寝不足のユーレイのように見えた自分、それまで美しいと思えていたものが美しく見えなくなってしまった自分、そして、そこからまったく閉塞状態に陥ってしまって這い上がれない自分自身と決別(「逃避」という単語は使いたくない)するためだった。
そして、毎日前進しているという確信が持てない「無力感」と、自分の理想と異なる方向へと進んでいっているかに思えた「絶望感」とに襲われることのない、まったく別の環境に身を置いて、自分というものをもう一度建て直したいという思い詰めた切望からであった。
そして以下の問答を行った。
問い:周りの環境をいかにして変えるか?
答え:思い切って外国で長期間住むのがいいだろう。
問い:外国に住むといっても、英語しかまともに学んだことがない自分がどこに住むのか?
答え:英語圏の国に住む場合、長期間滞在するにはその土地にて労働する必要がある。
問い:労働するといっても、労働ビザがそんなに簡単に取れる国があるのか?答え:アメリカ、イギリス、カナダはほとんど不可能に近いという。が、オーストラリアなら1年の労働ビザがもらえる。
以上がこの国へ来ようと決心したおおよその過程であったが、それは他の多くのワーキングホリデー旅行者のように、オーストラリアに恋焦がれてといったものでもなんでもなく、いわば消去法によって迷い込んだ袋小路から抜け出す唯一最後の突破口だったと言ってよい。
そして、なんとか人間としてもう一度自分を奮い立たせて日本へ帰るというのが、はるかこの南半球の、世界で最も孤立した都市といわれるパースまでやってきた最も基本的かつ最大の目標だったのだ。
先に掲げた三つの目標は、そいつを実現させるための最低限のステップとして、自分に課したものであった。
バレーをすることによって、より深くこの国の社会に入って行けるだろう。その過程で友人も増えるだろう。英語も上達するだろう。
そしてそこから自分自身にもう一度輝きを取り戻すことができることを・・・・、それをいま何にも増して望んでいる。
1985年5月E日
日本人会の野球の試合

今日、パース在住の日本人ビジネスマンチームと日本レストランチームの野球の対抗試合があった。パース在住の日本人の年一回の恒例行事となっているらしいが楽しいひと時だった。
自分はレストランチームの一員となって、5回をピッチャーとしてプレーしてくたくただ。こんなんではバレーボールなんかできんのんかいな、といささか不安になってくる。
ビジネスマンチームは東京六大学でホンモノの投手をしていたという人が投げて、われわれレストランチームは野次では勝ってはいたもののほとんど打てず、2試合やって2敗となった。まあ、日頃の不養生から考えれば、当然のことといえそうだが。
パース及び西オーストラリア州の日本人会には現在約300人のメンバーがいるそうである。別天地を求めて日本に見切りをつけ移住してきた人たち、ビジネス駐在員とその家族、戦争直後にオーストラリア軍兵士を看護しその後結婚移住したいわゆる戦争花嫁さん、そしてワーキングホリデー旅行者などがメンバーで、みんな和気あいあいとやっておられるようだ。
この後も日本人学校の文化祭、日本人会主催の運動会などの催しも予定されていると聞く。外国で暮らす緊張感からつかのま開放される機会をもつことは、特に言葉のハンディのある人には、やはり意義のあることだと思う。だが、やり過ぎはご法度。あくまでここは外国。自国の文化漬けになり過ぎてはいけない。
そして今日おもしろい人に会った。こちらに移住してもう10年になるという北口さんという人で、まだ32才ながらこの西オーストラリアではわが店のスズキ氏と並んで、日本人移住者の草分けの一人である。彼は現在パースにある西オーストラリア工科大学で、彼の勤める会社の社費により、学士号を取るべく勉強しているということだった。
彼はマウントニューマンという鉄鉱石を採掘・輸出している巨大な会社に勤めていて、1年前まで当州北部のポートヘッドランドという町で勤務していたが、なんとか学士号を取ってこい、との会社の命を受け、現在家族5人でパース暮らしなのだそうだ。
誰かからポートヘッドランド周辺の地域(一般にピルバラと呼ばれている)は人間の住むところなどでは絶対にないと聞かされていたため、そんなのいったいどんなとこなんやろ?と、以前からそのあたりの地域について少しは興味を持っていた。それゆえピルバラはこのパースを出たあとできれば訪れてみたいと思っていた地域でもあった。
詳しい話は何も聞けなかったが、この国で生きていくことについてインスパイアーされるものが、あの人から何か得られるかもしれない。わがレストランにもよく顔を出しておられるようだし、次に会う機会にはもっといろんなことを教えてもらおう。

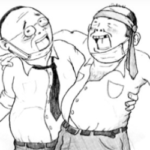

コメント